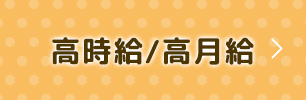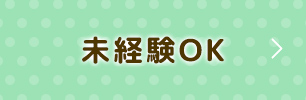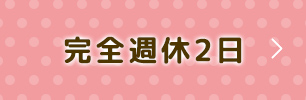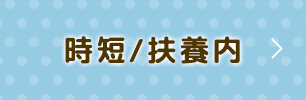食事介助とは、一人では食事をするのが困難な高齢者をサポートする仕事で、食事をするサポートや食前・食後の食事環境を整えたりします。
さらに、栄養補給のサポートだけでなく食事によってリラックスさせてあげるのも食事介助の役割です。
無資格からできますが、介助の方法や食事のコツなどがあるので把握しておくと業務で役立ちますよ。
この記事では、食事介助の方法や対応のコツなどを解説しているので、介護の仕事で食事介助を行う予定がある方はぜひ参考にしてください。
目次
介護職における食事介助とは?
食事介助とは、食事をするのが困難な方に対して食事に関するサポートを行う業務です。
利用者によって何が原因で食事が困難になっているかが違うため、一人ひとりに合わせた介助が必要で気を付けなくてはならないことが多くあります。
なかでも、高齢になると出てくる症状があるので、対策を練る参考にしてください。
【咀嚼力・嚥下力が弱くなる】顎や喉の筋肉が衰えることにより、咀嚼力(噛む力)と嚥下力(飲み込む力)が難しくなります。
食べ物を噛み切れない、食べ物をなかなか飲み込むことができないなど困難なことがあると食欲低下にもつながるので注意が必要です。
【唾液量が減る】嚥下力にもつながりますが、唾液量が減ると口の中の水分が減ってしまうような食べ物が食べづらくなります。
水分量が少ない食べ物食べられなくなると、食べられる種類が減ってしまって栄養の偏りの心配もあるのです。
【消化器官が弱くなる】年齢や薬などの影響で胃の機能が低下して消化器官が弱まっていることから空腹を感じづらく、食欲低下にもつながります。
食べ物の消化ができずに胃もたれのような体調の不調につながるため、消化や胃に優しい食べ物を与えるようにしましょう。
食事介助をするために必要な資格
冒頭でも話しましたが、食事介助の仕事は無資格からも可能です。
無資格でもできる介護の仕事は、食事介助を含む身体介助や施設内の環境整備、送迎、介護士補助などがあります。
しかし、介護職の調理やレシピの考案などはできないのでご注意ください。
介護職に関連した仕事をしたい場合は、介護職アドバイザーの資格が必要なので興味がある方は介護の資格を紹介している「介護で役立つ資格25種類の一覧」をご覧ください。
食事介助のコツ
ここからは、食事介助をするうえでの注意点やコツを解説します。
食事介助を行う予定がある方や食事介護業務がうまくいっていない方は、ぜひ参考にしてください。
清潔さを重視した準備
食事をするときは清潔さが大切なので、食事をする前にテーブルや食事に触れる手や口の洗浄を行いましょう。
また、ここで紹介する食事をするまでの準備中も利用者に声掛けをして食事への関心を高めていくことも必要です。
眠っていた方が目を覚ますための対策にもなりますし、体調チェックにもつながります。
排泄をすませる
食事中にトイレに行きたくなると、食事が中断されてしまします。
介護施設によっては部屋の中にトイレが設置されていることが多いため、食事中にトイレに行くと排せつ物のニオイが室内に漂い、食欲軽減につながります。
また、排泄の状態を見ることもできるので何か異変があったときは食事を変えたりして対策することも可能です。
テレビを消してテーブルの上をきれいにする
テレビがついたままだったりテーブルの上がごちゃごちゃしていたりすると、気がそれて食事に集中できません。
そのため、テレビを消すなどして食事がしやすい環境を整えましょう。
口を洗浄する
食事の前に口の汚れをなくしておきます。
うがいや歯磨きをし、食事と一緒に雑菌が体内に入り込まないように気を付けてください。
手を清潔にする
手の力が衰えている高齢者は、箸などをうまく使えないので、手で食べ物をつかんでしまうことがあります。
この際に手が汚れていると雑菌を体内にとりこんでしまう恐れがあるため、濡れタオルやウェットティッシュなどで手を拭いてきれいにします。
楽しい食事になるサポート
食卓が楽しくないと食欲も落ちてしまうので、食事をしっかり摂るためには楽しい食事になるサポートが大切です。
正しい姿勢で食事をしてもらう
食事は正しい姿勢で摂取しなくては誤嚥につながります。
深めに腰を掛けてもらって、背もたれは食べやすいように30~90度を目安に調節します。
しかし、人によっては姿勢を保つことが難しい方もいますので、一人ひとりに合わせた姿勢を見つけて食事介助をしていきましょう。
利用者と同じ目線で食事サポートをする
食事摂取のサポートをするときには、利用者の方を見下す格好にならないように注意しましょう。
目線を合わせられるように、椅子に座るなどしてサポートします。
適切な一口の量を探る
利用者にあわせて適切な一口を口に運ぶようにします。
目安はティースプーン一杯分を少し下の位置から口に運ぶようにするのが大切です。
また、利用者に食べやすいかの声掛けをして調整をしていくのも交流の一環になるのでおすすめです。
飲み込めているかの確認
喉の動きに注目して飲み込んだことをチェックして、次の一口を運ぶようにしましょう。
食事を急かさずに高齢者の食べるペースを尊重し、主食・おかず・野菜・味噌汁などを飽きないように交互に口へ運んでいきましょう。
食事中も「おいしいですね!」「食事をすると体があたたまりますよ!」といった声をかけるのも大切です。
食事の改善点を考える
食事介助の仕事は食事のサポートだけではなく、次回の食事で改善できるポイントがないかの対策も必要です。
不調が見つかったときは対策を練る
咀嚼力や嚥下力の低下や食欲不振など、食事中に気付いたことを覚えておいて対策を練る時に課題として報告しましょう。
食材を細かく刻んだりペースト状にして食べやすくしたり、消化に良い食事を用意するなど次回の食事で対策のために変えてもらえるようにしてください。
しかし、食材が細かすぎたりペースト状のままだったりすると美味しそうに見えなくなる恐れもあります。
味や栄養だけでなく、見た目も大切なので食欲が出るような工夫を忘れないようにしてください。
外食の計画を立てる
高齢者の中には、外食が好きな人もいます。
もし、食事制限が課されていないのであれば出前を取ったり家族からの差し入れを食べさせてあげたりする計画を立てることもおすすめです。
よくある質問
ここからは、食事介助に関する質問について解説していきます。
食事介助は未経験・無資格でもできますか?
未経験でも無資格でも食事介助は可能です。
施設によって細かいやり方は変わりますが、基本的に介護士の指導のもと行います。
しかし、あくまでも食事の手伝いなので調理やレシピの考案などは資格が必要になるのでご注意ください。
資格の有無については、こちらの「食事介助をするために必要な資格」でも解説しているので、あわせてご覧ください。
上手に食事介助を行うコツはありますか?
食事介助では、相手の様子を気遣うことが大切です。
その中でも、食事が楽しくなるようにして食べることに対する意欲が低下しないように食べやすくする工夫を考えていきましょう。
ほかにもいろいろなコツがあるので、くわしくは「食事介助のコツ」をご覧ください。
まとめ
高齢者は、喉や顎の筋肉が弱くなっているので、若いころのように食事ができなくなっています。
一人で食事が難しい利用者が楽しく食事ができるように、さまざまなサポートを行うのが食事介助です。
食事介助は、無資格でもできる業務ではありますが、高齢者や介護に対する深い知識があればよりスムーズな介助が行えるので資格取得を目指すことも検討しましょう。
食事のときは楽しい時間である方が食欲は増して、食べる意欲にもつながります。
サポートに集中することも大切ですが、この記事で話したポイントを抑えつつ一緒に楽しく食事ができるように心がけていきましょう。
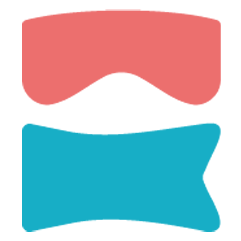
介護の仕事には経験や資格がなくてもできる業務がありますが、今回紹介した食事介助もその一つです。そのため、どのようなサポートをすれば良いか悩まれる方もいます。
介護職での仕事探しや悩みがある方は、ウィルオブ介護に相談をしてみませんか?介護職に特化していて、介護の現場にくわしい担当者がサポートしていきます。自分に合う働き方がわからなくても、やりたいことや希望条件などを考慮した提案をしてもらえますよ。